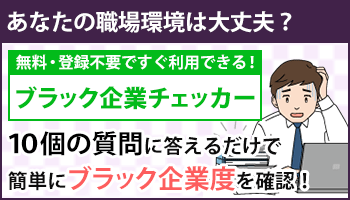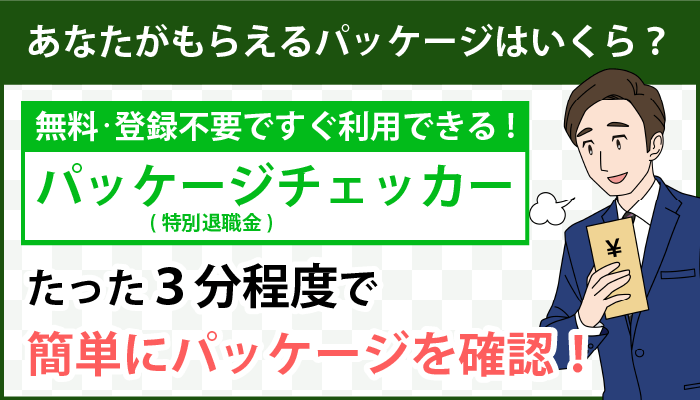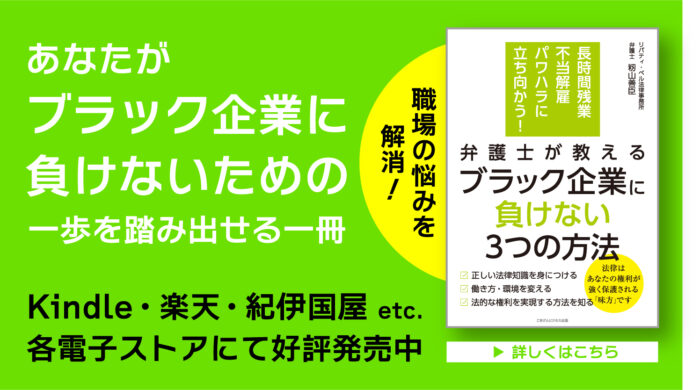近年、企業の人事管理の手段として転籍が行われることが増えています。もっとも、転籍により従業員の勤務環境に大きな変化が生じるため、必ずしもこれに応じることが従業員にとっても利益になるとは限りません。このような場合、従業員は転籍を拒否することはできるのでしょうか。今回は、転籍命令について解説します。
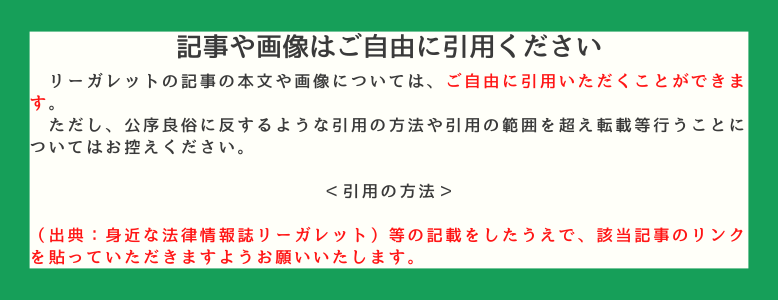
転籍とは
転籍とは、労働者が自己の雇用先の企業から他の企業へ籍を移して当該他の企業の業務に従事することをいいます。
つまり、労働者は、元の企業との労働契約関係を終了させて、新たに他の企業との間に労働契約関係を成立させることになります。具体的には、①現労働契約の合意解約と新労働契約の締結をする方法と、②労働契約上の使用者の地位の譲渡をする方法があります。
元の企業に籍を残さない点において、出向と区別されます。

転籍命令の可否
転籍には、労働者の同意が必要とされています。元の企業との労働契約が終了し新たな企業との労働契約が生じるためです。
そして、転籍についての同意は、入社時の包括的な同意や就業規則・労働協約上の「転籍を命じうる」旨の規定のみでは足りず、転籍先企業を示したうえでの個別的な同意であることを要します。
また、転籍についての同意が有効といえるには、一定期間後の復帰が予定され、転籍中の待遇にも十分な配慮がされるなどして、実質的に労働者にとっての不利益性がないことが必要です。
そのため、使用者が、労働者に対して、一方的に転籍を命じることはできません。転籍拒否を理由とする懲戒処分も原則として許されません。
従って、使用者から転籍を指示されたとしても安易に同意する必要はありません。転籍先や転籍後の労働条件などについて、十分に確認したうえで慎重に判断するべきです。
東京地決平4.1.31判時1416号130頁[三和機材事件]
「特に『出向』のうちでも、出向元との間の労働契約関係を存続させたまま出向先の使用者の指揮命令下で労務を提供するいわゆる『在籍出向』ではなく、出向によって出向前の使用者との間の労働契約関係が消滅し、出向先の使用者との間にあらたなる労働契約関係が生じる…いわゆる『転籍出向』の場合には、結果的には労働契約の当事者に交換的な変更を生じる点において労働契約の当事者には何らの変更のない配転とは決定的に異なる。」
「したがって、一方が実質的には独立の法人と認められないような場合はともかく、本件のように二つの実質的にも独立の法人格を有する会社の間においては、いかに前記のように労働条件に差異はなく、人的にも、資本的にも結び付きが強いとしても、法的に両会社間の転籍出向と一方の会社内部の配転とを同一のものとみることは相当でなく、転籍出向を配転と同じように使用者の包括的人事権に基づき一方的に行ない得る根拠とすることはできないというべきである。」
「また、これを実質的な面からみても、労働契約関係にあっては、労働者は継続的に労務を供給することによってその対価として賃金を得ていくのであるから、仮に転籍出向時点での労働条件に差異はなくとも、将来において両会社の労働条件に差異が生じる可能性があるとすれば、労働者にとってはどちらの会社との間に労働契約を締結するかということは転籍出向時点でも非常に重要な問題であり、そういう問題の生じない配転とは同一に扱うことはできない。」
転籍後の法律関係
転籍の場合には、元の企業との労働契約が終了しますので、労働契約上の使用者は、転籍先の企業のみとなります。
復帰が予定され、元の企業が賃金の差額を補填し続け、退職金も通算されるというような場合には、限定的に元の企業の労働保護法上または団体交渉上の使用者責任が問題となる余地があるとされています。





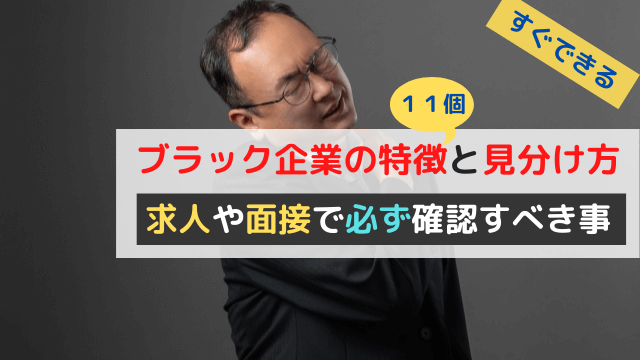











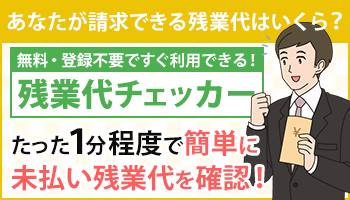
![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)