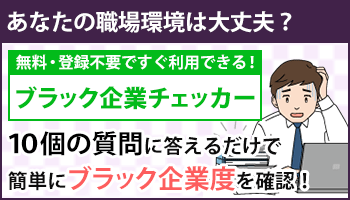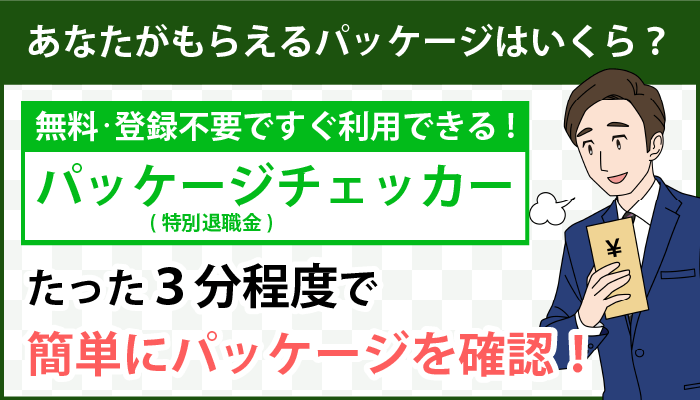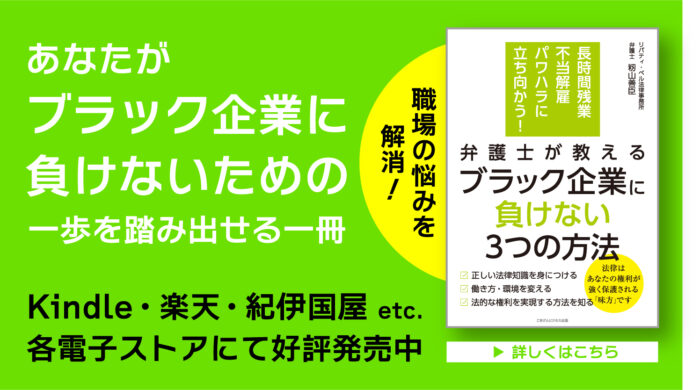会社に復職を求めたところ、これを拒絶された場合にはどうすればよいのでしょうか。休職期間満了により退職として扱うことは適法なのでしょうか。今回は、休職期間満了による自動退職と解雇について解説します。
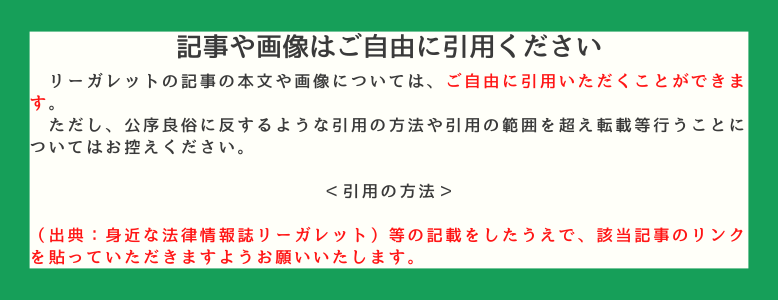
目次
休職制度の意義
休職とは、ある従業員について労務に従事させることが不能又は不適当な事由が生じた場合に、使用者がその従業員に対し労働契約関係そのものは維持させさながら、労務への従事を免除すること又は禁止することをいいます。休職制度には、傷病休職のほか、事故欠勤休職、起訴休職、出向休職、自己都合休職、専従休職等の種類があります。
休職制度の根拠
休職制度の内容については法律上の規制がありません。
休職制度は、就業規則や労働協約等の定めによることになります。もっとも、就業規則や労働協約等の定める効果がそのまま認められるとは限りません。裁判所は、これらの休職制度を、その目的、機能、合理性、労働者が受ける不利益の内容等を勘案して、就業規則の合理的解釈という手法で規制しています。
第〇条(休職)
1労働者が、次のいずれかに該当するときは、所定の期間休職とする。
①業務外の傷病による欠勤が2か月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないとき 6カ月以内
② 前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき 必要な期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、原則として元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に復帰させることが困難又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。
傷病休職事由
休職制度のうち、傷病休職制度は、一般に、労働者の業務外の傷病(私傷病)による欠勤が一定期間に及んだときに適用されます。傷病休職制度は、解雇又は退職を猶予して労働者の回復を待つ制度であり、その目的は一般に解雇猶予とされています。
会社が労働者に対して傷病休職を命じるためには、就業規則等に規定されている休職事由を満たす必要があるとされています。例えば、以下のような休職事由があります。
一定期間の欠勤
就業規則等には、休職事由として、「労働者の傷病による一定期間の欠勤事実」と定められている場合があります。
もっとも、一定期間の欠勤の事実については、客観的に明らかであることが多く、争点となることは多くありません。
業務支障
就業規則等には、休職事由として、「労働者の傷病による業務支障」と定められている場合があります。
「業務支障」については、休職が解雇猶予の性質を有する以上、それは解雇事由に相当する内容でなければならないと指摘されています。
⑴ 職務限定特約がある場合
労働者との間で職務限定特約がされている場合、使用者は、労働者の労働契約上の担当業務について労働者の疾病により業務支障が生じていることを主張立証する必要があります。
⑵ 職務限定特約がない場合
職種限定の特約がない場合、労働者が他業務での労務提供を申し出ていれば、使用者は、労働者の配置や従事可能な業務の存否の検討をしないと休職事由は認められません。
【最一小判平10.4.9集民188号1頁・労判736号15頁[片山組事件]】
「現に就業を命じられた特定の業務についての労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務についての労務の提供をすることができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である」
やむを得ない理由
就業規則等には、休業事由として、「前各号に準ずるやむを得ない理由があると認めた場合」と定められている場合があります。
東京高判平7.8.30労判684号39頁[富国生命保険事件]は、「その他前各号に準ずるやむを得ない場合」等に基づく休職命令につき、当該休職事由は、傷病休職の場合と実質的に同視できる程度に通常勤務を行うことに支障を来す場合にのみ該当するとしたうえで、休職事由該当性を否定しています。
傷病休職事由の消滅事由としての「治癒」
治癒の意義
傷病休職事由の消滅事由としての「治癒」とは、原則として、従前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復したときと解釈されています。
もっとも、現在の裁判例等の傾向としては、「治癒」したかどうかの判断においても労働者への配慮が求められる傾向にあります。
職種限定の特約がある場合
職種限定の特約がある場合には、特約がない場合に比べて、より上記「治癒」の定義が直截に妥当するとされています(札幌高判平11.7.9労判764号17頁[北海道龍谷学園事件])。
もっとも、職種限定の特約がある場合でも、当初軽作業に就かせれば程なく通常業務に復帰できる場合には、使用者にそのような配慮を行うことが義務付けられる場合があるとされています(東京地判昭59.1.27労判423号23頁[エールフランス事件]、大阪地判平11.10.18労判772号9頁[全日本空輸事件])。
職種限定の特約がない場合
職種限定の特約がない場合には、休職後の復帰に際し、現実に配置可能な業務の有無を検討すべきとされています(最一小判平10.4.9集民188号1頁・労判736号15頁[片山組事件])。
【大阪地判平11.10.4労判771号25頁[東海旅客鉄道事件]】
「労働者が職種や業務内容を限定せずに雇用契約を締結している場合においては、休職前の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、使用者の規模や業種、その社員の配置や異動の実情、難易等を考慮して、配置替え等により現実に配置可能な業務の有無を検討し、これがある場合には、当該労働者に右配置可能な業務を指示すべきである。そして、当該労働者が復職後の職務を限定せずに復職の意思を示している場合には、使用者から指示される右配置可能な業務について労務の提供を申し出ているものというべきである。」としました。
そのうえで、労働者が「身体障害等によって、従前の業務に対する労務提供を十全にはできなくなった場合に、他の業務においても健常者と同じ密度と速度の労務提供を要求すれば労務提供が可能な業務はあり得なくなるのであって、雇用契約における信義則からすれば、使用者はその企業の規模や社員の配置、異動の可能性、職務分担、変更の可能性から能力に応じた職務を分担させる工夫をすべきであ」るとし、退職扱いを無効としました。
治癒の立証責任
治癒の立証責任は、原則として、労働者にあると解されています(東京地判平25.1.31労経速2185号3頁[伊藤忠商事事件])。
もっとも、裁判例は、「使用者である企業の規模・業種はともかくとしても、当該企業における労働者の配置、異動の実情及び難易といった内部の事情についてまで、労働者が立証し尽くすのは現実問題として困難であるのが多いことからすれば、当該労働者において、配置される可能性がある業務について労務の提供をすることができることの立証がなされれば、休職事由が消滅したことについて事実上の推定が働くというべきであり、これに対し、使用者が、当該労働者を配置できる現実的可能性がある業務が存在しないことについて反証を挙げない限り、休職事由の消滅が推認されると解するのが相当である」と判示しています(東京地判平24.12.25労判1068号5頁[第一興商事件])。
自動退職規定の有効性
就業規則等により、休職期間が満了しても治癒(休職事由が消滅)しない場合には、期間満了によって当然に退職すると規定されている場合があります。これを自動退職規定といいます。
このような自動退職規定も有効に労働契約の内容になるとされています(東京地決昭30.9.22労民集6巻5号588頁[学校法人電気学園事件])。
もっとも、休職期間が解雇予告期間である30日を下回るような規定は、合理性を欠くものとして無効と考えられます。休職期間満了時に退職という効果を生ずる以上、傷病休職の発令は、実質的には解雇予告ないし条件付き解雇ともみることができるためです。
傷病休職を経ない解雇
休職制度がある場合にこれを経ずに解雇したとしても、これのみにより直ちに解雇が無効となるわけではありません。
もっとも、治癒の見込みがないことが明らかな場合(東京地判平14.4.24労判828号22頁[岡田運送事件])はともかくとして、そうでない場合は、使用者が、労働者に休職制度を適用できるにもかかわらず、これを適用しないで労働者を解雇した場合には、解雇権の濫用となる可能性が高いとされます。とりわけ、メンタル不調については、休職制度を適用しても治癒の見込みがないことが明らかとされるのは例外的な場合に限られます。(東京地判平17.2.18労判892号80頁[K社事件]等)




















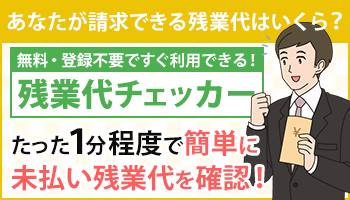
![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)