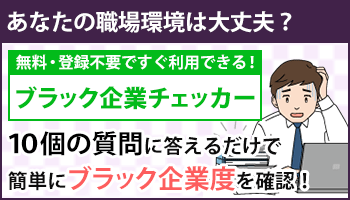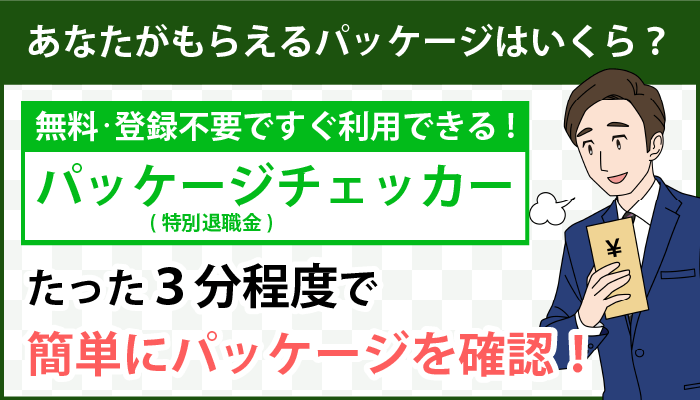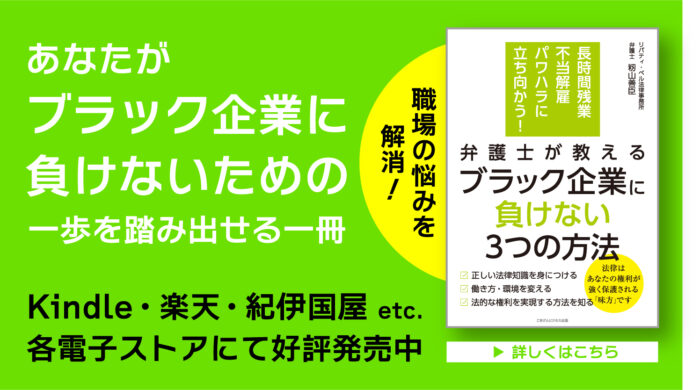退職届を会社に提出すると、会社から退職を認めないと言われたり、後任が決まるまでは残ってほしいと言われたりすることがあります。この場合、退職することはできないのでしょうか。また、会社の所定の書式で提出しないと退職を認めないことは許されるのでしょうか。今回は、辞職の時期や方法について解説します。
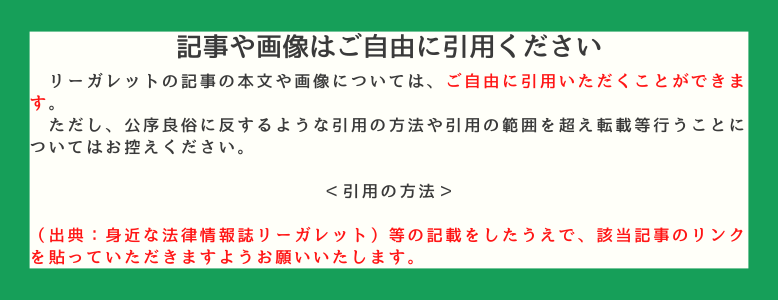
目次
辞職とは
辞職とは、労働者による労働契約の解約(退職)をいいます。
辞職については、労働基準法による定めはなく、民法により規制されています。そして、期間の定めのない労働契約と期間の定めのある労働契約で規制の内容が異なります。
期間の定めのない労働契約
民法の規制
期間の定めのない労働契約においては、労働者は2週間の予告期間を置けば、いつでも契約を解除できるとされています(民法627条1項)。
<平成29年民法改正以前>
平成29年民法改正以前は、「期間によって報酬を定めた場合」、つまり毎月1回払いの純然たる月給制(遅刻、欠勤による賃金控除なし)の場合には、解約の申し入れは次期以後についてすることができるとされ、その解約の申し入れは当期の前半にしなければならないとされていました(改正前民法627条2項)。そのため、月給制で末日締めの場合には、その月の前半に解約の申し入れ行い、来月以降に以後退職できることになります。
もっとも、平成29年民法改正により、民法627条2項の主体が「使用者」と限定されたため、改正民法の施行後は、純然たる月給制の場合にも、労働者は2週間の予告期間を置けば退職できることになります。
平成29年改正民法の施行時期は、平成32年(2020年)4月1日とされています。
民法627条(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
1項「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。」
2項「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」
3項「6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、三箇月前にしなければならない。」
就業規則等による規制の有効性
では、就業規則等により予告期間を2週間よりも長い1カ月などとすることは許されるのでしょうか。
従来、民法627条は、強行規定と解釈されており、予告期間を2週間よりも長くする定めは無効とされてきました。裁判例にも、民法627条の予告期間は、使用者のためには延長できないとして、2週間を超える予告期間の定めを無効としたものがあります(東京地判昭51.10.29判時841号102頁[高野メリヤス事件])。
もっとも、近時は、同条を任意規定と解した上で、不当に長期の予告期間は、公序の規定(民法90条)で個別に有効性を判断するべきとの考え方も唱えられています。
【東京地判昭51.10.29判時841号102頁[高野メリヤス事件]】
「民法第六二七条は、期間の定めのない雇用契約について、労働者が突然解雇されることによってその生活の安定が脅かされることを防止し、合わせて、使用者が労働者に突然辞職されることによってその業務に支障を来す結果が生じることを避ける趣旨の規定であるところ、労働基準法は、前者(解雇)については、予告期間を延長しているが(第二〇条)、後者(辞職)については何ら規定を設けていない。…」
「以上によれば、法は、労働者が労働契約から脱することを欲する場合にこれを制限する手段となりうるものを極力排斥して労働者の解約の自由を保障しようとしているものとみられ、このような観点からみるときは、民法第六二七条の予告期間は、使用者のためにはこれを延長できないものと解するのが相当である。」
期間の定めのある労働契約
民法の規制
期間の定めのある労働契約の場合には、期間途中の退職は、原則として認められず、例外として「やむを得ない事由があるとき」に限って認められます(民法628条)。
民法628条
「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。」
就業規則等による規制の有効性
期間の定めのある労働契約の場合には、やむを得ない事由がなくとも、就業規則等により2週間前の予告や1カ月前の予告により退職できるとすることは、民法よりも規制を緩やかにするものであり、有効と考えられます。ただし、やむを得ない事由があるときにも、直ちに契約を解除できず、予告期間を置くことを必要とする場合には、その有効性が問題になると考えられます。
所定の書式の退職届を求めることは許されるのか
会社が所定の所定の書式による退職届でないと退職を認めないとする場合があります。
もっとも、民法は解約の申し入れの方法を限定しておらず、所定の書式によらずとも、解約の意思が明確に使用者に伝われば、退職の意思表示は有効に成立しているものと考えられます。
就業規則等で「退職の申し出は、所定の書式の退職届による。」などとする規定があったとしても、他の方法による退職の意思表示の効果を否定することは難しいでしょう。
そのため、口頭やEmail、Line等であっても、有効に退職の意思表示の効果は発生します。もっとも、後日、証拠として残しておくために、口頭は避けた方がいいでしょう。
なお、可能な限り自分で作成した退職届を提出した方が安全ですが、会社が所定の書式の退職届を求めるのは事務処理上の便宜の場合もあります。そのため、所定の書式による退職届の作成に協力した方が円満な退職に資することもあります。もっとも、会社の所定の書式の退職届に労働者に不利益な条項が含まれている場合もありますので、その記載内容はよく確認するようにしてください。
通知人は、本書面により、令和●年●月●日をもって、貴社を退職させていただく旨の意思表示をいたします。
退職の理由は伝えなければならないのか
期間の定めのない労働契約における辞職は、労働者の一方的な意思表示により行うことができるとされているため、労働者は辞職の理由を必要とすることなく退職できます。
これに対して、期間の定めのある労働契約における期間内の辞職の場合には、「やむを得ない事由」が必要となりますので、辞職の理由を伝える必要があるでしょう。
また、一方的な辞職ではなく、合意退職の申し入れの場合には、会社が承諾するかどうかを判断するために退職の理由を伝えるべき場合があります。
年次有給休暇
就業規則に「従業員が退職しようとするときは、一四日前に退職届を提出し、現実に勤務しなければならない。」などの規定がある場合には、その間、退職届の提出後、年次有給休暇を取得することはできないのでしょうか。
裁判例は、退職届提出後の14日間に現実に勤務しなかった場合に退職金を支給しないとの覚書につき、「退職日から遡つて所定労働日の一四日間に限つて年次有給休暇の取得を制約されるにすぎず…、しかも、退職日及び退職届出日の設定は労働者において任意に設定でき、かつ、年次有給休暇の取得もそれをも考慮して任意に消化できることも考え併わせると、右のような制約があるからといつて、それをもつて前記覚書の規定の効力を妨げる事由とは認め難い」と判示したものがあります(第1審:大阪地判昭57.1.29労働判例384号69頁、控訴審:大阪高判昭58.4.12労判413号72頁[大宝タクシー事件])。

損害賠償
辞職は、上記の規定に従って行われ、辞職までの間に業務引継ぎなどの労働義務を誠実に果たす限り適法であり、辞職それ自体につき損害賠償責任は生じません。
退職の効力が生じるまでの2週間につき有給休暇を取得するなどして会社に出勤せず、業務の引継ぎなどを全く行わない場合などには、損害賠償責任が問題となる場合があります。使用者が、引継ぎの不履行による損害の立証をすることは困難とされていますが、争いとなることを避けるため、引継ぎの方法につき使用者と協議したり、文書により引継ぎ内容をメモして交付したりしておくのがよいでしょう。
また、2週間の予告期間を置かない突然の退職については、労働者の損害賠償責任を認めた裁判例がありますので注意が必要です(東京地判平4.9.30労判619号[ケインズインターナショナル事件])。
【東京地判平4.9.30労判619号[ケインズインターナショナル事件]】
労働者が2週間の予告期間を置かずに退職し、使用者が取引先との契約関係を維持できず、これにより少なくとも1000万円の得べかりし利益を喪失し、労働者がこれにつき200万円の損害を賠償すると合意した事案につき、同裁判例は以下のように判示しています。
「期間の定めのない雇用契約においては、労働者は、一定の期間をおきさえすれば、何時でも自由に解約できるものと規定されているところ(民法六二七条参照)、本件において、被告は原告に対して、遅くとも平成二年六月一〇日ころまでには、辞職の意思表示をしたものと認められないではないから(そうすると、月給制と認められる本件にあっては、平成二年一月一日以降について解約の効果が生ずることになる。)、原告が被告に対し、雇用契約上の債務不履行としてその責任を追及できるのは、平成二年六月四日から同月三〇日までの損害にすぎないことになる。」
「さらにはまた、労働者に損害賠償義務を課することは今日の経済事情に適するか疑問がないではなく、労働者は右期間中の賃金請求権を失うことによってその損害の賠償に見合う出捐をしたものと解する余地もある。」
「以上のような点を考え合わせれば、本件においては、信義則を適用して、原告の請求することのできる賠償額を限定することが相当である。」
その他諸般の事情を総合考慮すると、「原告が被告に対して請求することができるのは、本件約定の二〇〇万円のおおよそ三分の一の七〇万円…に限定するのが相当である。」

退職代行業者
退職代行業者とは、労働者の自分自身で使用者とのやり取りをすることなく、会社を辞めたいというニーズに応えるために出現した業者です。労働者に代わり使用者に対して退職の意思を伝え、これに対して対価が発生することになります。
弁護士や弁護士法人でない業者が労働者に代わり退職の意思を伝えることが許されるのかについては議論があるところです。
弁護士法72条は、「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。」と規定しています。
使用者に対して退職の意思表示を行うことは、労働契約の終了という法律上の効果を発生させるものです。そのため、弁護士又は弁護士法人でない退職代行業者は、労働者の代理人として意思表示を行うことはできません。
これについて、退職代行業者は、退職の意思表示をするのは本人であり、退職届自体を本人に作成させるなどして、それを使用者に届ける使者に過ぎないとの位置づけを用いている例が多いです。
使用者は、退職代行業者から退職届が届いた場合には、まず本人の真意(本当に退職代行業者に依頼したのか、本当に退職の意思を有しているのか)を確認する対応を行うことが多いです。退職代行業者の文書の中に、本人への直接のコンタクトを禁じる文言や、退職代行業者宛てに連絡をしてほしい旨の依頼文言が入っていても、それに拘束力はなく、本人に連絡する方法により真意を確認されることもあります。これにより、労働者の真意が確認できた場合には退職として扱い、真意が確認できない場合には無断欠勤などとして自動退職や懲戒解雇とされる場合があります。ただし、懲戒解雇については、弁明の機会の付与等の観点から認められない場合が多いでしょう。





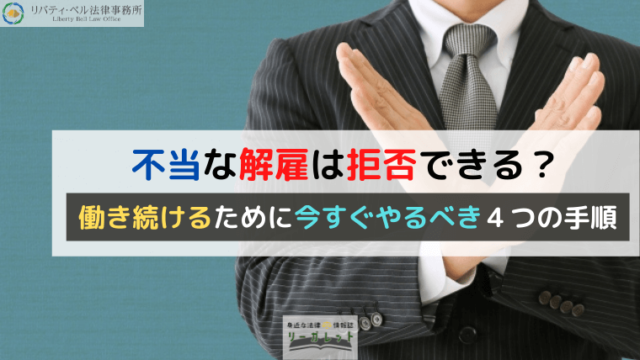














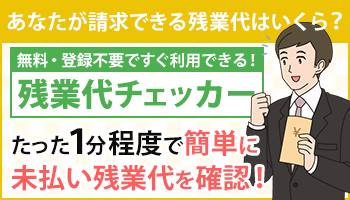
![不当解雇チェッカー 不当解雇チェッカー[サイドバナー]](https://legalet.net/niwp/wp-content/uploads/2021/04/ca864075b616dde00bfeb899345fd9a6.jpg)